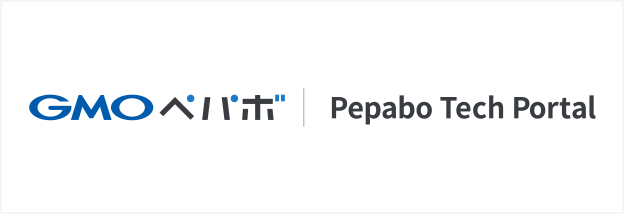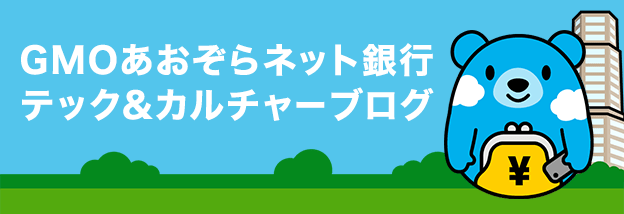BYODとは、組織の許可を得たうえで従業員が個人所有のデバイスを業務で使用することを指します。
具体的には、スマートフォンやタブレット、ノートPCなどの個人デバイスに業務用アプリケーションをインストールして業務を実行します。
端末調達コストの削減や従業員の生産性向上といったメリットに期待できますが、同時に情報漏洩のリスクやプライバシー侵害の恐れなどのデメリットも存在するため注意が必要です。
この記事では、BYODの概要やメリット・デメリット、BYOD導入時のセキュリティ対策について解説します。
目次
[ 開く ]
[ 閉じる ]
- BYODとは
- BYODが普及した背景
- BYODを導入するメリット
- 企業側のメリット
- 端末購入のコストを削減できる
- シャドーITの対策になる
- 生産性向上に繋がる
- 従業員側のメリット
- 端末管理の負担が軽減される
- 使い慣れた端末で業務を行える
- BYODを導入するデメリット
- 企業側のデメリット
- 情報漏洩のリスクがある
- 従業員の労働状況を把握しづらくなる
- 通信費用に関するルールを策定する必要がある
- 従業員側のデメリット
- プライベートとの分別がつきにくくなる
- プライバシーを侵害される恐れがある
- BYOD導入時に取るべきセキュリティ対策
- BYODガイドラインを策定する
- 従業員のセキュリティ教育を実施する
- VPNを導入する
- アンチウイルスソフトを導入する
- 端末管理ツールを活用する
- BYODの安全性を高める「MDM」と「MCM」
- MDM
- MCM
- まとめ
BYODとは

BYODとは「Bring Your Own Device」の略称で、組織の許可を得たうえで従業員が個人所有のデバイスを業務で使用することを指します。
スマートフォンやタブレット、ノートPCなどの個人デバイスを企業システムに接続し、業務に活用する働き方の形態です。
従来は企業が支給する専用端末での業務が一般的でしたが、BYODでは個人の端末に業務用アプリケーションをインストールしたり、クラウドサービスにアクセスしたりすることで業務を実行します。
この取り組みにより、従業員は使い慣れたデバイスで効率的に業務を進めることができ、企業側も端末調達コストの削減や柔軟な働き方の実現といったメリットを得られます。
BYODが普及した背景
リモートワークの急速な拡大により、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方が強く求められるようになったことが背景にあります。
同時に、「Microsoft 365」や「Google Workspace」などのクラウドサービスが広く普及し、個人デバイスからでも企業システムへの安全なアクセスが技術的に実現しやすくなったことも要因の1つです。
若年層を中心とした従業員の働き方に対する価値観の変化も、BYOD普及を後押しする重要な要素といえるでしょう。
BYODを導入するメリット

BYOD導入は企業と従業員の双方にとって多くの利点をもたらし、現代の多様な働き方を支える重要な取り組みとなっています。以下、BYODを導入する主なメリットを紹介します。
企業側のメリット
まずは、企業側のメリットを3つ紹介します。
端末購入のコストを削減できる
class="font-bold">従業員の個人デバイス活用により、企業が負担する端末調達費用を削減できます。
特に大規模組織では数百台から数千台の端末調達が不要になるほか、ハードウェアの保守管理費用も発生しません。
また、端末の故障対応や定期的な買い替えコストも従業員負担となり、コストの軽減効果が期待できます。
シャドーITの対策になる
シャドーITの対策になる点もBYOD導入の大きなメリットです。
シャドーITとは、組織が使用を許可していない、もしくは従業員が利用していることを組織が把握・管理していないITツール・サービスのことです。
従業員による無許可のデバイス利用を完全に防ぐことは困難ですが、BYODの導入により、これまで把握できなかった私用端末の業務利用を正式な管理下に置くことで、セキュリティリスクの軽減が期待できます。
シャドーITの詳細については以下の記事をご覧ください。
生産性向上に繋がる
従業員が普段から使い慣れたデバイスで業務を行うことで、操作効率と作業スピードの向上が期待できます。
通勤時間やちょっとした空き時間でも業務処理を行えるようになります。
また、新しい端末の操作方法を覚える必要がないため、研修コストの削減と即戦力化も実現できるでしょう。
従業員側のメリット
続いて、従業員側のメリットを2つ解説します。
端末管理の負担が軽減される
複数のデバイスを使い分ける必要がなくなり、日常的な端末管理が大幅に簡素化されます。業務用と個人用の端末を統一することで、持ち運びの負担が軽減されるのです。
データの同期や設定の統一も自動的に行われるため、端末管理にかける時間と労力を本来の業務に集中させることができます。
使い慣れた端末で業務を行える
普段から使用している操作性やインターフェースで業務が行えるため、新たな学習コストが不要になります。
慣れ親しんだデバイスの操作感により作業効率が向上します。個人的に愛用しているアプリケーションとの連携も可能で、より柔軟な業務スタイルを実現できるでしょう。
BYODを導入するデメリット

BYOD導入には企業と従業員の双方にリスクとデメリットが存在するため、慎重な検討が必要です。セキュリティリスクから労務管理の課題まで、さまざまな問題への対策を講じることが重要です。
企業側のデメリット
以下、企業側のデメリットを3つ解説します。
情報漏洩のリスクがある
個人デバイスから重要な企業情報が流出する可能性があり、従来の境界型セキュリティでは対応困難な新たなリスクが生まれます。
個人使用のアプリケーションや不正なWi-Fi接続、マルウェア感染により、意図しないデータ漏洩が発生した場合、企業の機密情報保護に深刻な脅威をもたらします。
情報漏洩の原因や具体的なリスクについては以下の記事をご確認ください。
従業員の労働状況を把握しづらくなる
個人デバイスの使用により勤務時間の境界が曖昧になるため、過重労働や長時間労働の発見が遅れる可能性があります。
労働基準法に抵触するリスクも高まり、企業の法的責任問題に発展する恐れもあるのです。
勤怠管理システムとの連携が不十分な場合、正確な労働時間の把握自体が困難になることもあるでしょう。
通信費用に関するルールを策定する必要がある
業務利用分の通信費負担について、詳細で公平な基準を設ける必要があります。
個人利用と業務利用の区別が困難で、適切な費用按分方法の確立が複雑な課題となります。従業員間での不公平感を避けるため、透明性の高い制度設計が求められるでしょう。
従業員側のデメリット
次に、従業員側のデメリットを2つ解説します。
プライベートとの分別がつきにくくなる
個人デバイスでいつでも作業ができることで、プライベートとの分別がつきにくくなります。
オンオフの切り替えが心理的に難しくなり、結果としてワークライフバランスの悪化や職場ストレスの増大に繋がる可能性があります。
プライバシーを侵害される恐れがある
企業による端末監視やセキュリティソフトの導入により、個人情報が意図せず把握されるおそれがあり、プライバシーが侵害される可能性があります。
個人的な連絡先やアプリケーションの使用状況が企業に知られることで、従業員の精神的ストレスの蓄積に繋がる可能性もあります。
BYOD導入時に取るべきセキュリティ対策

BYOD環境では従来の境界型セキュリティが通用しないため、多層防御による包括的なセキュリティ対策が必要です。以下、企業が取るべき対策を5つ紹介します。
BYODガイドラインを策定する
禁止事項を明文化した包括的なルールを作成することが重要です。
従業員が守るべき行動規範を具体的に示し、違反時の処分についても明確に定めておく必要があります。
▼BYODガイドラインの例
- パスワード設定の複雑さ
- アプリケーションのインストール制限
- 公共Wi-Fi利用時の注意点
- 業務利用の範囲
- BYOD展開の方針
ガイドラインは定期的に見直しを行うことが求められます。
新たな脅威や技術の進歩に対応した内容に更新し、常に最新のセキュリティ環境に適応させましょう。
従業員のセキュリティ教育を実施する
定期的な研修を通じてセキュリティ意識の向上を図り、BYODに伴うリスクと対処法を従業員に教育します。
フィッシング攻撃の見分け方、不審なアプリケーションの識別方法、データ漏洩を防ぐ具体的な行動など、実践的なスキルを身につけさせることが重要です。
模擬的なサイバー攻撃訓練も効果的な教育手法として活用されます。
さらに、従業員の理解度を測定するテストや、セキュリティインシデント発生時の対応手順についても継続的な教育が必要となります。
VPNを導入する
暗号化された安全な通信経路を確立することで、外部ネットワークからのアクセス時でもデータ送受信の安全性を確保します。
外部ネットワークからでも社内システムと同等の高いセキュリティレベルを維持することが期待できます。
特に公共Wi-Fiや不安定なネットワーク環境からの業務アクセス時には、VPNによる保護が不可欠であり、通信内容の盗聴や改ざんを効果的に防ぐことが可能です。
コンプライアンス要件を満たす安全な業務環境を構築することが求められます。
アンチウイルスソフトを導入する
マルウェアやウイルスの侵入を防ぎ、個人デバイスと企業データの両方を保護する包括的なセキュリティ対策を実施します。
定期的なスキャン機能やヒューリスティック検知により、既知の脅威だけでなく未知のマルウェアも検出し、被害発生前に対処できるようになります。
アンチウイルスソフトは常に最新の定義ファイルに更新することが重要です。
端末管理ツールを活用する
デバイスの一元管理により、セキュリティポリシーを統一的に適用し、企業全体のセキュリティレベルを標準化します。
遠隔操作によるデータ削除や機能制限を行うことで、紛失時や盗難時の被害を最小限に抑えられるのです。
また、デバイスの使用状況や位置情報の監視を行えば、異常な活動を早期に検知し、セキュリティインシデントの未然防止を図れます。
BYODの安全性を高める「MDM」と「MCM」

MDMとMCMはBYOD環境におけるセキュリティ強化の中核技術として位置付けられ、企業データの保護と従業員のプライバシー確保を両立します。
MDM
MDMは「Mobile Device Management(モバイル端末管理)」の略称で、デバイス全体を包括的に管理するシステムです。
デバイス全体を統制し、セキュリティポリシーの一括適用により、組織全体の統一されたセキュリティレベルを実現します。
▼MDMの主な機能
- 端末の設定変更
- アプリケーションのインストール制限
- デバイスの紛失・盗難対策
紛失時の遠隔ロックやデータ消去機能により、機密情報の漏洩リスクを最小化します。
ただし、従業員の個人利用部分も管理対象となるため、プライバシーの観点から慎重な運用が求められます。MDMの詳細については以下の記事をご覧ください。
MCM
MCMは「Mobile Contents Management(モバイルコンテンツ管理)」の略称で、企業データのみを対象とした管理システムです。
企業データのみを対象とした管理により、従業員のプライバシーを保護しながら必要なセキュリティ対策を実現します。
業務用アプリケーションとデータを専用領域に隔離し、個人利用部分には一切干渉しないため、従業員の心理的負担やストレスを軽減できる仕組みです。
また、退職時には企業データのみを選択的に削除することが可能です。
まとめ
この記事では、BYODの概要やメリット・デメリット、セキュリティ対策について解説しました。
BYODを導入すれば、端末調達コストの削減や従業員の生産性向上といったメリットを得ることができます。
一方で、情報漏洩リスクやプライバシー侵害といった課題もあるため、BYODを導入する場合は適切なセキュリティ対策が必要です。
企業側、従業員側のメリット・デメリットを考慮したうえで、BYODの導入を検討してみてください。
文責:GMOインターネットグループ株式会社