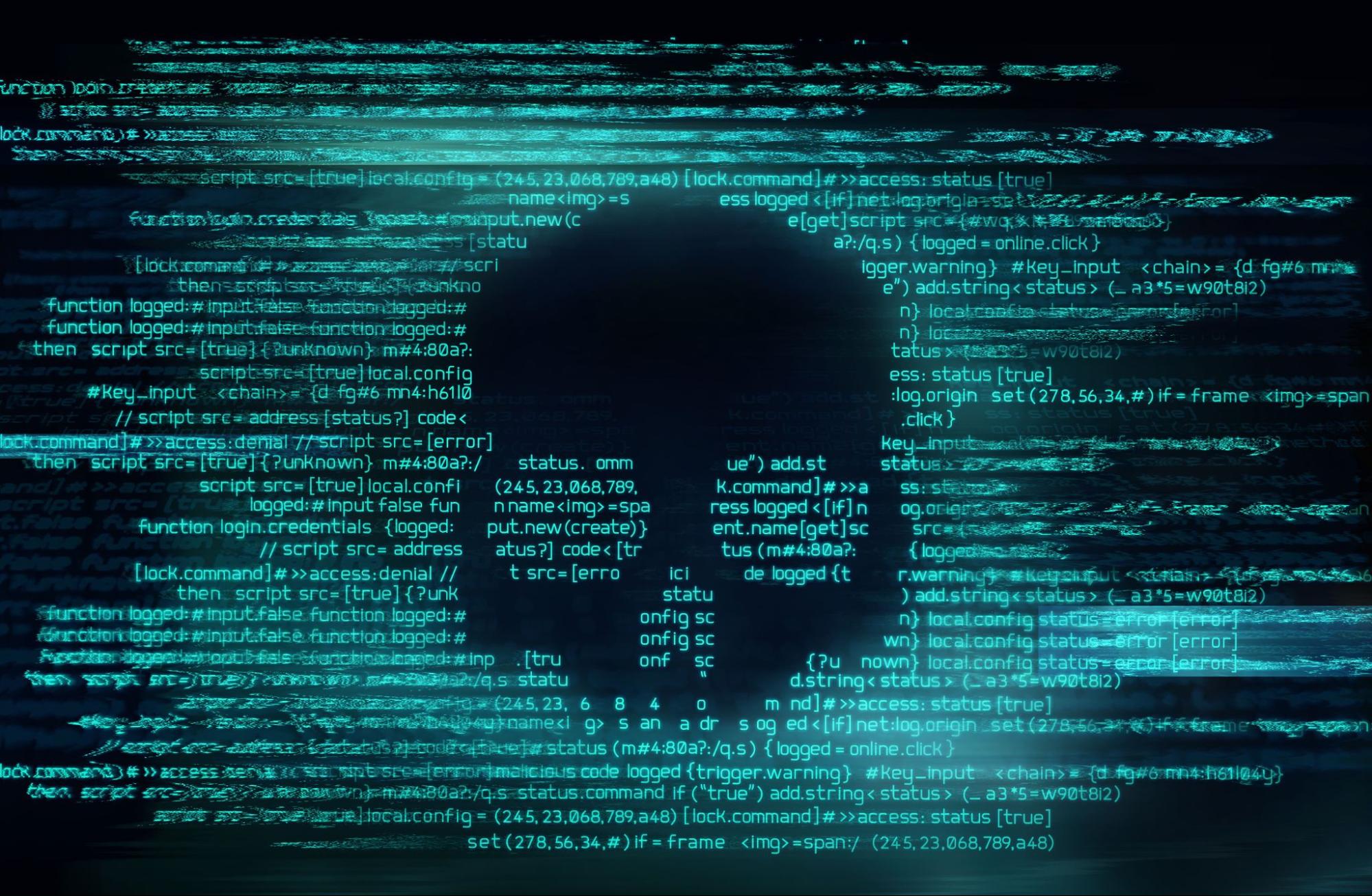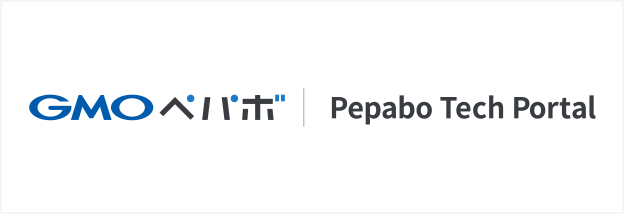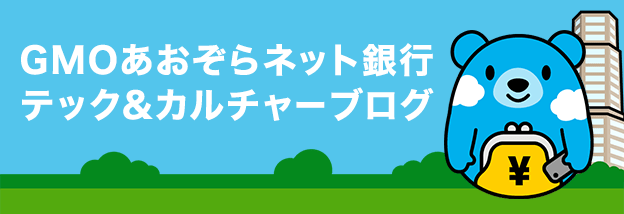「eKYCとは何か、なぜ導入が進んでいるのか、メリット・デメリットを知りたい」という疑問がある方もいるでしょう。
eKYCとは、デジタル技術を活用した非対面の本人確認システムのことです。
2018年の法改正により正式に認められ、AI技術や生体認証、ICチップ読み取りなど先端技術により高度な安全性を実現しています。
しかし、スマートフォン操作に不慣れなユーザーの離脱や、撮影品質がユーザーに委ねられるといったデメリットが存在するのも事実です。
この記事では、eKYCの導入理由、技術的進化と安全性、メリット・デメリット、導入時の重要ポイントについて解説します。
目次
[ 開く ]
[ 閉じる ]
- eKYCとは
- KYCとの違い
- eKYCが導入された背景
- eKYCの導入が進んでいる理由
- 本人確認の厳格化
- 適用範囲の拡大
- 非対面や非接触のトレンド
- マイナンバーカードの普及
- eKYCの技術的進化と安全性
- 画像認証技術
- 暗号化技術
- ライブネスチェック
- ICチップ情報と3Dセンサー
- ブロックチェーン技術
- eKYCによる本人確認の種類
- 6条1項1号ホ
- 6条1項1号へ
- 6条1項1号ト
- 6条1項1号ワ
- eKYCの主な利用シーン
- 法規制に基づいている場合
- 自主利用の場合
- 企業がeKYCを導入するメリット
- 本人確認手続きの負担軽減に繋がる
- 郵送や印刷のコストを削減できる
- セキュリティレベルの向上に寄与する
- 企業がeKYCを導入するデメリット
- 一部ユーザーの離脱を招く恐れがある
- 操作がユーザーに委ねられる
- eKYCの導入事例
- 銀行の口座開設アプリ
- 中古品のオンライン買い取り
- インターネットチケットの購入
- eKYCサービスを導入する際の重要ポイント
- 本人確認方式
- 組み込み先との相性
- 導入・運用のしやすさ
- ベンダーのセキュリティレベル
- アフターサービスの充実度
- GMOグローバルサインの顔認証eKYC
- まとめ
eKYCとは

eKYCとは、スマートフォンやタブレット、PCなどのデジタルデバイスを用いて、オンラインで本人確認を行うことを指します。
「Electronic Know Your Customer」の略称であり、従来の対面や郵送による本人確認に代わる、効率的で迅速な方法として注目されています。
eKYCでは、顔写真付きの公的証明書や生体情報などを利用し、遠隔地からでも確実に本人確認を行うことが可能です。
これにより、金融機関や行政サービスにおいて、非対面での取引や手続きを安全かつスムーズに行うことができるようになりました。
KYCとの違い
KYCが従来の対面による本人確認プロセスを指すのに対し、eKYCはデジタル技術を活用した非対面での本人確認を実現するものです。
従来のKYCでは、スタッフによるチェックのために店舗への来店や書類の郵送が必要でした。
しかし、eKYCなら自宅にいながら数分で手続きが完了するため、時間的・地理的制約から解放されます。
AI技術の自動判定により人的コストを削減し、24時間365日の対応も実現しています。
eKYCが導入された背景
eKYCは2018年の「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯収法)」施行規則の改正により、正式に認められるようになりました。
この背景には、オンラインサービスの普及に伴い、非対面での本人確認ニーズが高まったことがあります。
インターネットバンキングや電子契約など、オンライン上で完結するサービスが増加する中、従来の対面や郵送による本人確認では、利便性や効率面での課題が指摘されていました。
eKYCの導入により、これらの課題を解決し、オンラインサービスの利用促進と利用者の利便性向上を図ることが期待されています。電子契約の仕組みは以下の記事で詳しく解説しています。
eKYCの導入が進んでいる理由

デジタル化の進展により、オンラインでの本人確認需要が急速に増加しています。ここでは、eKYCの導入が進んでいる具体的な理由について解説していきます。
本人確認の厳格化
マネーロンダリングや不正取引対策の強化により、本人確認の重要性が一層高まっています。
eKYCは、AIや生体認証技術を活用することで、高精度な本人確認を実現します。これにより、なりすましや不正利用のリスクを低減することが可能となっているのです。
金融機関をはじめとする事業者にとって、eKYCは規制対応と顧客保護の両立に欠かせないツールとなっています。
適用範囲の拡大
当初は金融機関を中心に導入が進んでいたeKYCですが、近年ではその適用範囲が大きく拡大しています。
EC業界や不動産業界、クラウドファンディングなど、さまざまな業界でeKYCの活用が進んでいるのです。
オンラインでの取引や契約が増える中、eKYCの利用シーンも多様化しています。業界の垣根を越えて、eKYCはデジタル社会における本人確認インフラとしての地位を確立しつつあります。
非対面や非接触のトレンド
新型コロナウイルス感染症の拡大を機に、非対面・非接触のサービス提供が求められるようになりました。
そんな中、eKYCはこのトレンドに合致した本人確認手段として一層注目を集めました。
eKYCを活用すれば、対面での手続きが難しい状況下でも、オンラインで安全かつ迅速に本人確認を行えます。
ニューノーマル時代の本人確認ソリューションとして、eKYCへの期待は高まる一方です。
マイナンバーカードの普及
マイナンバーカードの普及率向上に伴い、ICチップ読み取りによる正確な本人確認が現実的になりました。
総務省の「マイナンバーカード交付状況について」によると、2025年4月時点でのマイナンバーカードの保有枚数は約1億件に達しています。人口に対する保有枚数率は78.5%です。
政府は健康保険証廃止や運転免許証との統合など、本人確認のマイナンバーカード原則一本化を進めています。
この流れに伴い、いまよりも幅広い場面でオンライン本人確認の需要が拡大していくと予想されます。
eKYCの技術的進化と安全性

eKYCは、画像認証や生体認証などの先端技術を組み合わせることで高度な安全性を確保しています。以下、eKYCの技術的進化と安全性について解説します。
画像認証技術
最新の画像認証技術は本人確認書類の微細な印刷パターンや特殊加工まで検証します。
AI技術の発達により、従来は人の目でしか判別できなかった偽造の痕跡も自動検出が可能となりました。
また、運転免許証やマイナンバーカードといった本人確認書類だけでなく、利用者本人の顔を撮影することで、書類内容と一致しているかを確認できます。
明るさ・手ぶれ・解像度といった基本的な要素から、より高度な判定まで幅広く対応しているのです。
暗号化技術
eKYCシステムでは、個人情報を保護し安全なデータ転送を実現しています。
送信される画像や個人データは強固な暗号化技術によって保護され、通信経路での情報漏洩リスクを排除します。
データベース内での個人情報も暗号化して保存されているため安心です。これは、万が一の不正アクセス時でも情報の悪用を防ぐ仕組みです。
暗号化の仕組みについては以下の記事をご確認ください。
ライブネスチェック
ライブネスチェックとは、写真や動画の「なりすまし」を防ぐ技術のことです。
単純な顔写真による本人確認の場合、事前に撮影された画像や印刷物を使った偽装は難しくありません。
しかし、ライブネスチェックを取り入れ、利用者本人に「顔を左右に動かす」「まばたきをする」などの動作を要求することで、実在する人物であることをリアルタイムで確認できます。
画像や動画を利用したなりすましを防ぎ、より確実な本人確認が可能となりました。
ICチップ情報と3Dセンサー
運転免許証やマイナンバーカードなどに搭載されたICチップから直接情報を読み取ることで、情報の改ざん防止を実現しています。
また、スマートフォンに搭載された3Dセンサーを活用し、顔の立体構造を正確に把握することで、平面の画像では認識できなかった細部の確認も可能となりました。
これらICチップ情報と3Dセンサーの採用により、本人確認書類の偽装や不正利用のリスクを軽減できています。
ブロックチェーン技術
将来的に期待されているのがブロックチェーン技術の活用です。
ブロックチェーン技術では、暗号化技術を使って認証情報をブロック単位でまとめ、記録を分散的に共有することで情報の改ざんを困難にします。
分散型台帳の特性を活かし、一度記録された認証情報は事実上変更不可能な状態で保管できます。
また、認証情報を安全に保管・再利用することで、複数サービスでの本人確認手続きを簡略化可能です。
eKYCによる本人確認の種類

eKYCには、犯収法に基づくさまざまな本人確認方法が存在します。以下、eKYCによる本人確認の種類を4つ紹介します。
6条1項1号ホ
6条1項1号ホは、写真付き本人確認書類と本人の容貌画像を利用した確認方法です。
利用者は、マイナンバーカードや運転免許証などの公的証明書を撮影した後、本人の容貌を撮影した画像を添付して事業者に送信します。
事業者は画像データに記載された情報と、利用者が入力した情報を照合することで、本人確認を行います。
この方法では、写真付き本人確認書類の原本を直接撮影しなければなりません。また、原則として撮影後すぐに送信する必要があります。
比較的シンプルな方法であり、幅広い業種での導入が進んでいます。
6条1項1号へ
6条1項1号へは、ICチップ付き本人確認書類と顔写真の組み合わせによる確認方法です。
必要となるのは、マイナンバーカードや運転免許証などのICチップ付き証明書と、本人の容貌を撮影した画像データの計2点です。
本人確認書類に埋め込まれたICチップを用いて、氏名や住所、生年月日などの本人情報を読み込み、画像データと照らし合わせることで本人確認を行います。
ICチップによる高度なセキュリティ確保と、顔写真による本人性の担保を両立した方法といえるでしょう。
6条1項1号ト
6条1項1号トは、金融機関もしくはクレジットカード会社と連携することで確認する方法です。
この方法を利用する際は、写真付き本人確認書類の画像データ1点、もしくはICチップ情報と銀行口座やクレジットカード情報を事業者に提供します。
事業者は、金融機関などに照会することで、本人確認書類の真正性や口座の有効性を確認します。
比較的手間がかかる方法であるため、他の確認方法に比べてあまり普及していません。
6条1項1号ワ
6条1項1号ワは、マイナンバーカードのICチップをスマートフォンで読み取る確認方法です。
利用者は、マイナンバーカードをスマートフォンにかざし、ICチップ内の情報を読み取ります。
その上で、J-LISが提供する公的個人認証サービスを経由することで、オンラインでの本人確認が完了します。J-LISとは、地方公共団体情報システム機構のことです。
政府が推進するマイナンバーカードの普及促進とも連動した将来性の高い方法として期待されています。
eKYCの主な利用シーン

eKYCは金融機関での口座開設から不動産契約、シェアリングサービスまで幅広い分野で活用されています。
ここでは、eKYCの主な利用シーンを「法規制に基づいている場合」と「自主利用の場合」に分けて紹介します。
法規制に基づいている場合
多くの業界では法的要請により、eKYCを含む本人確認が必須要件となっています。
銀行やクレジットカード会社などの金融機関が代表的で、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯収法)」によって口座開設や高額取引において厳格な本人確認が求められています。
この規制は金融機関だけでなく、リース会社や不動産業者、貴金属取扱事業者なども対象です。
法務関連では司法書士や弁護士などの士業も該当し、業務の性質上本人確認が不可欠です。
▼規制対応が必要な主要分野
- 銀行・証券会社での新規顧客受付
- 消費者金融・カードローン申込み
- 賃貸住宅・売買物件の契約手続き
- モバイル通信サービスの新規契約
- 中古品売買・質屋営業での取引
- 法的手続きに関わる専門サービス
自主利用の場合
法的義務がない分野でも、サービス品質向上や安全性確保を目的としてeKYC導入が拡大しています。
プラットフォーム型ビジネスでは利用者同士のトラブル回避や信頼関係構築のため、積極的な本人確認を実施する企業が増加傾向にあります。
特に注目されるのがシッティング関連サービスです。ベビーシッターなどが代表的で、利用者の安全を最優先に考えた厳重な事前審査が業界標準となりました。
そのほか、エンターテインメント分野では転売対策として、チケット販売時の本人確認が定着しています。企業の顧客サポートにおいてもeKYCが活用されるケースが目立ちます。
▼自主導入が進む主要分野
- ソーシャルメディア・ネットワークサービスの登録
- イベント参加・チケット購入
- カーシェア・民泊などのシェアリング利用
- 資格試験・検定のオンライン受験
- 自治体手続きの電子申請システム
企業がeKYCを導入するメリット

eKYCの導入により、企業は業務効率化やコスト削減、顧客満足度向上などのメリットを得られます。
以下、企業がeKYCを導入することで得られる主なメリットを3つ紹介していきます。
本人確認手続きの負担軽減に繋がる
eKYCを導入すれば、従来の対面や郵送による本人確認と比べ、処理時間を大幅に短縮できます。
オンラインで完結するため、24時間365日いつでも本人確認が可能となり、顧客の利便性が大きく向上するのです。
さらに、書類の整理・保管に要していた工数も削減できるため、業務効率化に大きく寄与します。
郵送や印刷のコストを削減できる
本人確認書類の郵送や保管にかかるコストの大幅な削減にも繋がります。
従来の紙ベースの本人確認では、書類の印刷や封入、発送などに多くの経費がかかっていましたが、eKYCならこれらのコストを丸ごと省くことが可能です。
また、書類の保管スペースや管理工数も不要となるため、総合的なコスト最適化に大きく貢献するでしょう。
セキュリティレベルの向上に寄与する
eKYCではAIによる高精度な画像解析により、なりすましなどの不正を防止することができます。
また、本人確認情報をデジタルデータとして一元管理することで、紛失や改ざんのリスクを大幅に抑えられます。
従来の紙ベースの本人確認と比べ、情報漏洩のリスクを格段に低減できる点は、大きなアドバンテージといえるでしょう。
企業がeKYCを導入するデメリット

eKYC導入にはメリットがある反面、いくつかの課題や懸念点も存在します。
企業がeKYCを導入する際は、以下のようなデメリットを十分に理解し、適切に対応することが求められます。
一部ユーザーの離脱を招く恐れがある
スマートフォンなどのデジタル機器の操作に不慣れな高齢者などが、eKYCの利用を敬遠する可能性があります。
手続きの複雑さや操作への不安から、サービスの利用そのものを控えてしまう恐れがあるのです。
利用者の属性を考慮し、わかりやすい説明や代替手段の用意など、きめ細やかな対応が必要となります。
eKYCの導入に際しては、こうしたユーザー離れのリスクを十分に理解しておくことが重要です。
操作がユーザーに委ねられる
eKYCでは、ユーザーが自身で本人確認書類を撮影するため、画像のブレや不鮮明さが生じやすいという問題があります。
スムーズに完了せず撮影回数が多くなったりするとユーザーの離脱に繋がりかねません。撮影方法や注意点を丁寧に説明し、ユーザーの理解を促すことがポイントです。
また、AIによる画質チェックやガイダンス機能の充実など、技術的な工夫も求められるでしょう。
eKYCの導入事例

さまざまな業界でeKYCの導入が進んでおり、具体的な活用事例が増えています。
各業界の特性に合わせた効果的な活用方法が確立されつつあります。以下、eKYCの導入事例を3つ紹介します。
銀行の口座開設アプリ
銀行業界では、スマートフォンアプリを通じて、短時間で口座開設手続きを完了させるeKYCの活用が進んでいます。
来店不要で24時間365日いつでも口座開設の手続きが可能となるため、顧客の利便性が大幅に向上しています。
さらに、行員の事務負担軽減にも繋がっており、業務効率化の観点からもメリットは大きいといえるでしょう。
中古品のオンライン買い取り
eKYCの活用により、中古品のオンライン買い取りがスムーズに行えるようになりました。
従来は事業者が集荷時に本人確認を行っていたため、集荷に対応できる場所は限られていましたが、eKYCを導入したことでリアルタイムでの本人確認が可能となり、出荷場所を指定できるようになりました。
スムーズな買い取り手続きが実現できており、従業員の負担軽減にも繋がっています。
インターネットチケットの購入
チケット販売では不正転売防止のため、購入時にeKYCによる本人確認を実施するケースが増えています。
チケット購入時にeKYCで本人確認を行うことで、なりすましや不正購入を防止し、公平なチケット販売を実現できています。
本人確認の手間を最小限に抑えつつ、不正行為を効果的に抑止できる点が、eKYCならではのメリットといえるでしょう。
eKYCサービスを導入する際の重要ポイント

eKYC導入時には、自社のビジネスモデルに適切なサービスを選定する必要があります。以下、サービスを選ぶ際の重要ポイントをそれぞれ解説します。
本人確認方式
自社サービスに適切な本人確認方式を選択することがユーザーの離脱率低減に繋がります。
本人確認書類と顔認証の簡易タイプから、ICチップ読み取りを併用する高セキュリティタイプまで選択肢は幅広く存在します。
| ホ方式 | 写真付き本人確認書類の撮影+本人の容貌撮影 |
|---|---|
| へ方式 | ICチップ付き本人確認書類+本人の容貌撮影 |
| ト方式 | 写真付き本人確認書類またはICチップ情報+銀行口座またはクレジットカード情報 |
| ワ方式 | マイナンバーカード+スマートフォンでのICチップ読み取り |
業界の法的要件や取り扱う情報の機密レベルに応じて、最適なセキュリティレベルを設定することが重要です。複数の認証方法を採用すればセキュリティと利便性を両立できます。
組み込み先との相性
既存システムやアプリケーションとの互換性が高いeKYCサービスを選定することが重要です。
システムとうまく連携できない場合、大規模なシステム改修が必要となります。APIの充実度や開発サポート体制を評価し、スムーズに統合できるサービスを選ぶべきです。
eKYCサービスによって導入できるシステムが異なる場合もあるため、スムーズに連携できるかどうかを事前に確認しましょう。
導入・運用のしやすさ
初期設定の容易さや管理画面の使いやすさがシステム定着の重要な要素となります。自動化機能の充実度や例外処理への対応力は、日常的な運用負荷に直結します。
ユーザー目線の操作性については、非技術者でも直感的に操作できるインターフェース(UI)が理想的です。
わかりやすく操作しやすいUIであれば、ユーザーは本人確認をスムーズに進められ、結果としてサービス満足度の向上に繋がりやすくなります。
ベンダーのセキュリティレベル
サービスを導入する際には、eKYCベンダー自身のセキュリティ対策レベルや第三者認証取得状況を必ず確認しましょう。
個人情報を扱うサービスだけに、ベンダーのセキュリティ体制が不十分であれば重大なリスクとなります。
公式サイトの情報やユーザーレビューだけでなく、ISMS認証やプライバシーマーク(Pマーク)取得などの客観的指標を基に評価することがポイントです。
また、定期的なセキュリティ監査の実施状況も重要な判断材料となります。
アフターサービスの充実度
技術的問題発生時の対応スピードや手厚いサポート体制が長期的な安定運用を左右します。eKYCサービスの停止は事業活動に直接的な影響を与えるためです。
ヘルプデスクの対応時間や専任担当者の有無など、サポート体制の充実度を比較検討しておきましょう。
また、システム障害時の対応体制も事前確認が必要です。定期的なシステムメンテナンスやアップデート時の事前通知体制も、安定運用には重要な要素といえます。
GMOグローバルサインの顔認証eKYC

画像引用元:GMOグローバルサイン
「GMOグローバルサイン」の顔認証eKYCは、AIを活用した高セキュリティなオンライン本人確認サービスです。
25年以上にわたるSSL証明書認証局運営で培ったセキュリティノウハウを基盤として開発しており、犯罪収益移転防止法や古物営業法など各種法律に準拠した本人確認をオンラインで実現します。
スマートフォンのWebブラウザで完結する簡単な操作性を持ちながら、運転免許証・マイナンバーカード・在留カードなど主要な身分証明書に対応しています。
▼業界・シーンの導入例
- 古物商:物品買取、売出
- チケット販売:不正取引防止
- レンタル:レンタル品貸し出し
- 不動産:賃貸/駐車場契約時
月額20,000円・確認回数50件のAPI連携タイプと、月額50,000円・確認回数500件のメール送信タイプの2種類を用意しています。eKYC導入を考えている方は、お気軽にご相談ください。
まとめ
この記事では、eKYCの導入理由、技術的進化と安全性、利用シーン、メリット・デメリット、導入時の重要ポイントについて解説しました。
eKYCはAI技術や生体認証により高度な安全性を確保し、24時間365日の本人確認や業務効率化、コスト削減を実現できます。
金融機関での口座開設から自治体手続きの電子申請システムまで幅広い分野で活用が進んでいます。
「GMOグローバルサイン」の顔認証eKYCは、25年以上のセキュリティノウハウを基盤とした高セキュリティなオンライン本人確認サービスです。eKYC導入をお考えの場合はぜひご検討ください。
文責:GMOインターネットグループ株式会社